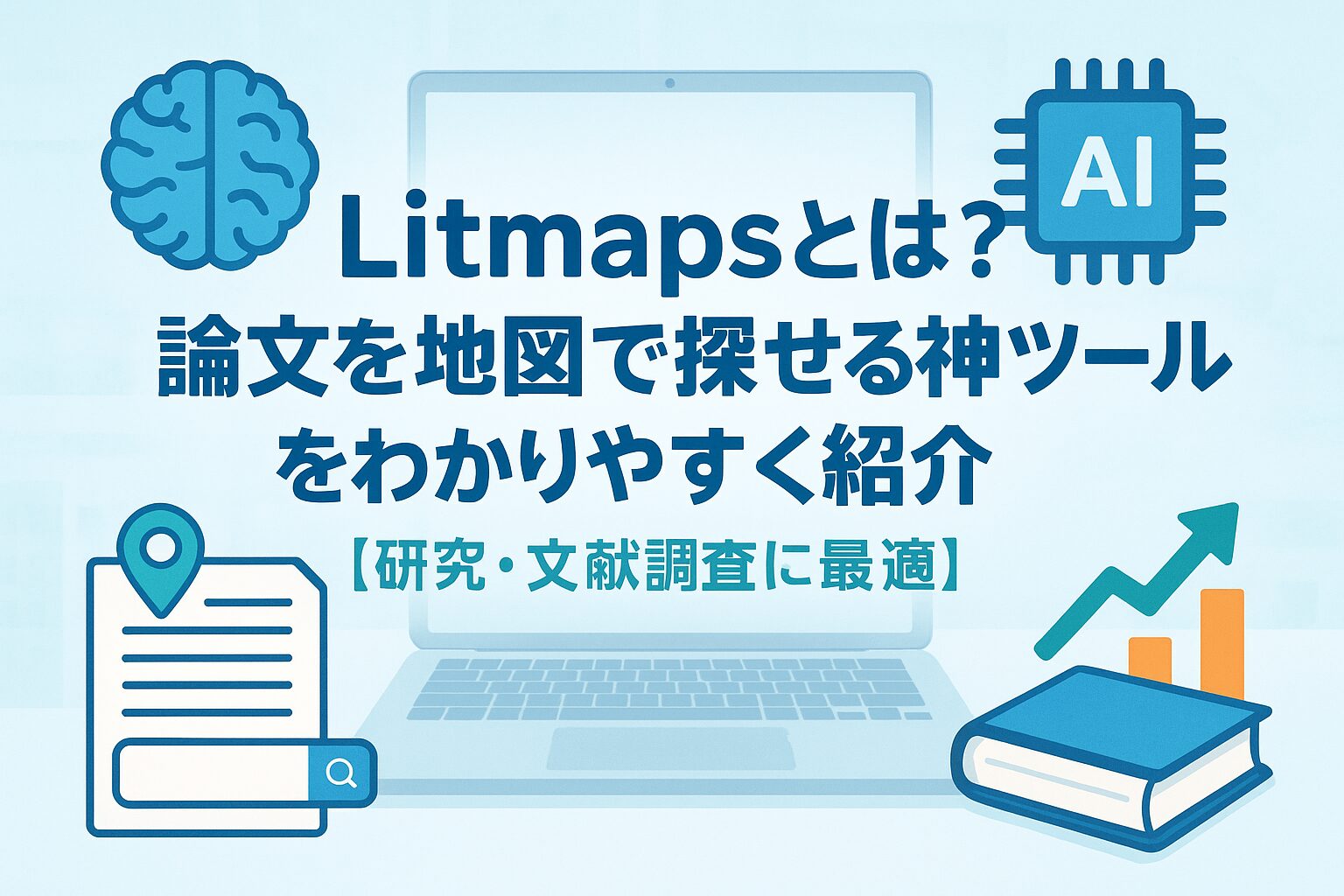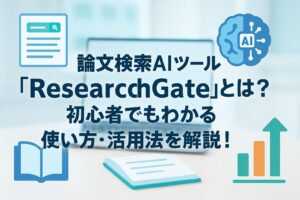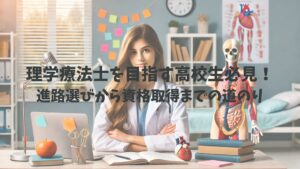学術論文を探すとき、「どこから手をつけていいかわからない」「関連する論文を見つけるのが大変」そんな悩みを感じたことはありませんか?
今回は、そんな悩みを解決してくれるAIツール「Litmaps(リットマップス)」について、初心者にもわかりやすくご紹介します。
⬇︎こちらで役立つAI一覧が見れます!⬇︎
LitmapsってどんなAI?
Litmapsは、研究者や学生が論文を視覚的に整理・発見できるAIツールです。
従来のようにキーワードで検索するだけでなく、関連する論文を地図のように図で表示してくれるのが最大の特長です。
まるで地図を見ながら目的地を探すように、自分の関心に近い論文を次々と発見できます。
「どんな論文が関係しているのか」「研究の流れはどうなっているのか」が一目でわかるので、文献調査がスムーズになるのです。
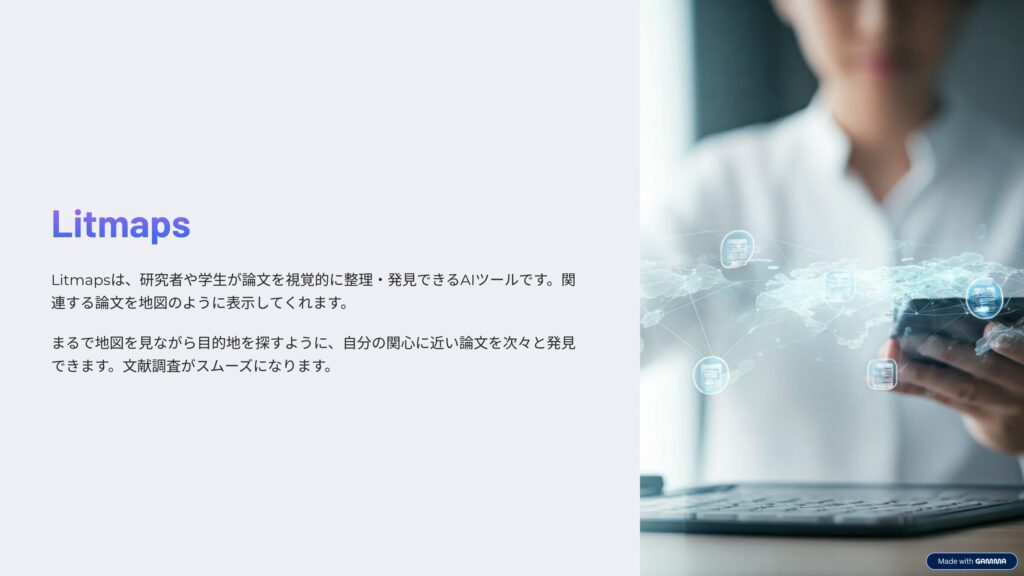
Litmapsでできること
初心者にも嬉しい、Litmapsの主な機能を紹介します。
1. 関連論文を“地図”で見られる
Litmapsは、ある論文を起点にすると、その論文と関連する他の論文をネットワーク図のように表示してくれます。
これにより、「どの論文がどれに影響を与えているのか」「どれが最近のトピックか」などがひと目でわかります。
2. 自分だけの論文マップを作れる
気になる論文をマップ上にまとめておけば、自分専用の「研究地図」が完成。
時間が経っても、自分が何を調べていたか、どこまで読んだかをすぐに確認できます。
3. 新しい論文を自動で教えてくれる
「自分が気になる分野の論文が新しく出たら知りたい!」という人に嬉しい機能が「アラート通知」。
自分のマップに関連する新着論文を自動で教えてくれるので、常に最新情報をキャッチできます。
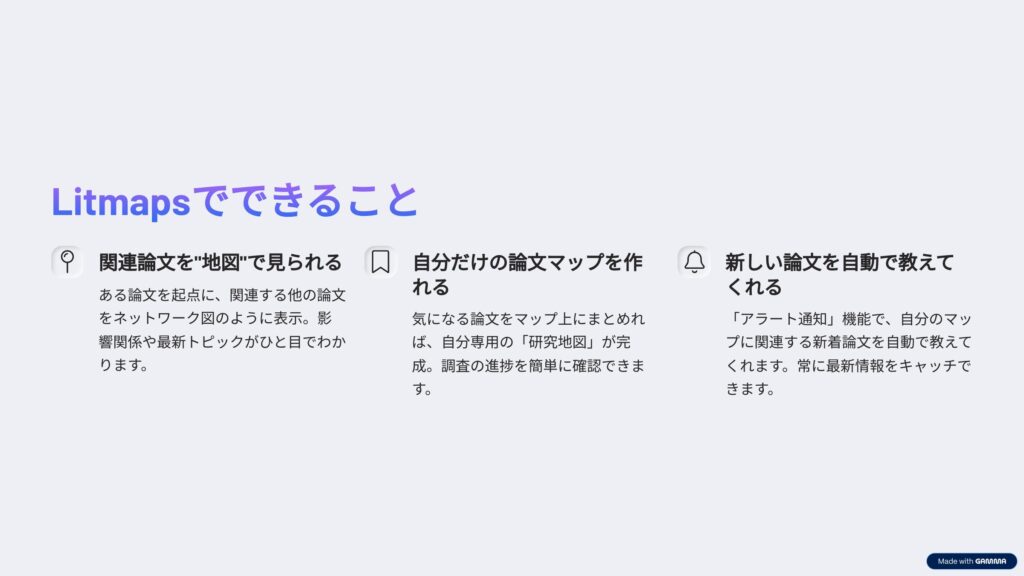
Litmapsの使い方
「使い方が難しそう…」と思う方も安心してください。Litmapsは直感的に使えるデザインになっています。
ステップ1:アカウント登録
まずは公式サイト(Litmaps公式サイト)にアクセスし、無料アカウントを作成します。
ステップ2:論文を検索
検索ボックスに調べたいキーワードや、気になる論文のタイトルを入力します。
ステップ3:マップを作成
表示された論文を「Add to Map(マップに追加)」ボタンで自分のマップに登録。
これで、関連論文が自動で表示され、地図のように展開されます。
ステップ4:関連論文をチェック
マップ上のノード(点)をクリックすると、論文の要約やリンクが表示されます。そこから実際の論文を読みに行くこともできます。
ステップ5:アラート設定
マップ右上の「Alert」ボタンをクリックすると、自分の研究テーマに関する新着論文を自動で教えてくれるようになります。
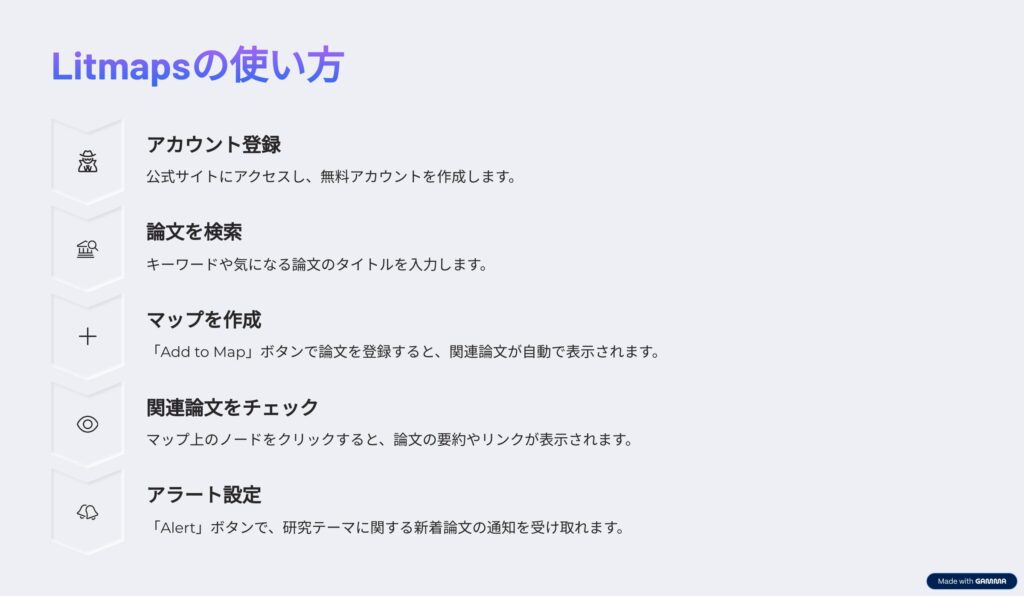
一緒に使うと便利なAIツール
Litmapsだけでも便利ですが、以下のAIツールと組み合わせることで、さらに効率的に研究できます。
・Research Rabbit
Litmapsと同様に論文を可視化してくれるツール。両方使って比較するのも◎
・Connected Papers
一つの論文を中心に、その周囲の論文をネットワーク形式で表示
・Elicit
質問を入力すると、関連する論文を要約付きで探してくれるAI
・Semantic Scholar
AIを活用して関連性の高い論文を推薦してくれる検索エンジン

よくある質問(FAQ)
Q1:Litmapsは無料で使えますか?
A:はい、基本機能は無料で使えます。ただし、高度なマップ保存数や通知数などを増やしたい場合は、有料プランにアップグレードする必要があります。
Q2:日本語の論文にも対応していますか?
A:Litmapsは主に英語の論文を対象としています。日本語の論文は少なめですが、英語で検索することでより多くの情報が見つかります。
Q3:スマホでも使えますか?
A:現在、Litmapsはパソコンのブラウザ利用が推奨されています。スマホでもアクセスは可能ですが、操作性はやや落ちます。
Q4:論文の全文も読めますか?
A:マップ上に表示される論文は、多くが外部リンク付きです。そこから全文が読めるかどうかは、その論文の公開状況によります(オープンアクセスなら全文OK)。
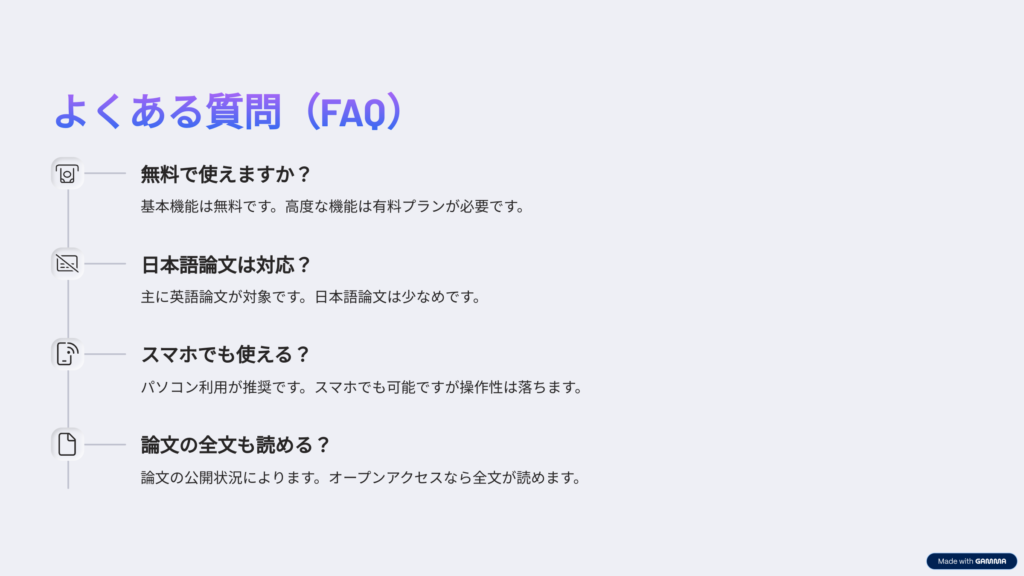
まとめ
Litmapsは、論文探しを地図のように視覚化してくれるAIツールです。
初心者でも使いやすく、視覚的に理解できるのが大きな魅力。
ElicitやConnected Papersなどと一緒に使うことで、もっと効率よく研究を進めることができます。
論文を探すのが面倒に感じていた人こそ、ぜひ一度使ってみてください!